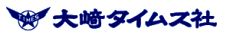おおさきオープンイノベーションチャレンジ2025「高校生ビジネスアイデアコンテスト」(おおさき産業推進機構主催)の審査が22日、大崎市役所で開かれた。審査の結果、古川黎明高2年の女子生徒グループ(5人)が発表した、市内産シュンギクを使ったスムージーの販売プランが最優秀賞に選ばれ、賞金10万円が贈られた。将来を担う高校生らがビジネスに関心を高め、将来、地元で起業し地域振興に貢献してほしいと初めて開催。大崎市内の高校の生徒と、市内に学習拠点を置く仙台高等専門学校の学生による11グループと4人が参加。10月に応募を締め切った後、企業経営者らから指導を受けアイデアを磨き、プレゼンテーションの方法など学んでコンテストに臨んだ。会場には教員や保護者、一般も含め40人ほどが訪れ発表を見守り、大学教授や企業経営者、伊藤康志市長ら5人が審査を行った。生徒、学生らはデジタル技術を活用した災害時の外国人支援やボランティアのマッチング、野生動物の被害対策などアイデアを提案。事業化の課題など審査員の質問に答えた。
古川署、鳴子署、加美署と県山岳遭難防止対策協議会(県山遭協)鳴子、加美両支部救助隊は21日、冬山遭難に備えた合同の捜索救助訓練を大崎市鳴子温泉のオニコウベスキー場で行った。5団体から合わせて35人が参加し、雪に埋まった人の救助手順や道具の使い方などを確かめた。この日は、全国的に多発しているバックカントリースキー中の遭難事故を想定。参加者は歩行練習を兼ねスノーシューを履いて現場へ向かい、雪庇の高低差を利用して穴を掘り、1・5㍍ほど上から「ゾンデ棒」を雪に突き刺して穴に入った人や装備、遺留品の感触を確かめた。続いて、位置情報を頼りに送受信機「ビーコン」を捜索。機動隊員が誰にも知らせずに遭難者に扮しており、参加者は掘った雪の下から現れた人間に驚きながらも「要救助者発見」と声を上げ、助け出していた。
JA古川園芸振興会の「大感謝祭マルシェ」が20日、古川農協狐塚野菜集出荷場で開かれた。多くの人が訪れ、朝収穫されたばかりの新鮮野菜や、県が開発した試験栽培中のイチゴの新品種などを買い求めていた。マルシェは、古川産の野菜をアピールしようと、同振興会(斉藤彰人会長)が昨年7月にスタート。毎月1回、同集出荷場で開いている。この日は本年度最後の開催。朝収穫したばかりのダイコンやカブ、シュンギク、トマトなどが並び、レジの前には購入した人の列ができていた。旬を迎えたイチゴは「もういっこ」など3種類を販売。このうち「みやぎi3号」は、県が新たに導入を目指し試験栽培中の品種。「もういっこ」と「おおきみ」を掛け合わせて育成したもので、実が大きく多収なのが特徴。
美里町は19日、来年度始める新規施策を盛り込んだ農業施策についての説明会を、町中央コミュニティセンターで開いた。持続可能な地域農業に向け、担い手創出や空き家バンク制度と連携した農地集積、移住定住促進に取り組む旨を説明した。新たな農業施策は、4月から4年間取り組む第2次町総合計画・総合戦略の第3期基本計画に基づく。本年度まで進めている集落営農組織法人化や農地集積・集約化を一部改める。担い手確保に向け、大・中規模経営体を地域農業の中心に位置づけ、経営効率化や経営力強化を促す。農地集積・集約や経営規模拡大、経営基盤強化、需要に応じた作物生産、所得安定化を支援するほか、新規就農者確保、企業の参入支援に取り組む。農地流動化を目指し、農地賃貸借関連制度や手続きについて周知を徹底、マッチングや相談体制の強化も図る。農地や水利施設の管理を含む共同活動を支える。畜産経営安定化に向けては畜産農家や関係事業者が連携し、地域ぐるみで高収益型畜産を実現する体制「畜産クラスター」を支援する。
大崎市は18日、クマ被害対策の一環で、管理されていない「放任果樹」の伐採を始めた。クマを呼び寄せる可能性が高い人里近くの果樹を切り、生活圏への出没を防ぐ取り組み。初日は岩出山中で安全祈願祭も執り行い、関係者が業務中の無事故、無災害を祈った。本年度はクマの出没にとどまらず、人身被害や農作物被害も全国的に多発。大崎市でも秋から年末にかけて目撃が相次ぎ、昨年10月には市民がクマに襲われて負傷したり、庭につないでいた飼い犬が連れ去られたりする被害が起きた。これを受け市は10月から12月まで緊急事態宣言を発令し、独自の取り組みとして伐採を希望する放任果樹を土地所有者から募集。このうち、住宅や事業所、作業場に近いクリやカキなど約1800本が伐採の対象となった。人が普段いない空き家近くの果樹や実のならない樹木は含まれない。
美里町合併20年を記念した音楽祭「兆し」が15日、町文化会館で開かれた。町の次代を担う小中学生を中心とするさまざまな世代の住民らが演奏を披露し、古里の大きな節目を飾った。同館(早坂美名子館長)が主催したもので、大崎タイムスなど後援。町内の小中学生や高校生、太鼓・ダンスサークルのほか、町外のスポーツクラブやすずめ踊りサークルなど9団体が出演した。昨年4月に開校した美里中の吹奏楽部員らでつくる「美里サウンズ」は、小牛田農林高吹奏楽部と共演。総勢40人が織りなすハーモニーと音の厚みで聴衆を魅了した。童話「オズの魔法使い」をテーマとした南郷小マーチングバンドの演奏、演技も会場を沸かせた。
日本遺族会が第2次世界大戦の経験を語り継ぐ「平和の語り部」が13日、大崎市大貫小(伊藤礼子校長、児童数70人)であった。県内3校目、県北部では初めての実施。6年生が戦争の悲惨さと平和の尊さについて、遺族の話を通して考えた。同会は戦後80年となる本年度までの3年間、全国で語り部活動の強化を図っている。県内では、角田市角田小(1月)と岩沼市岩沼南小(同)に続く開催で、歴史の授業で大戦について学ぶ6年生を対象とした。同校を訪れたのは、大崎市古川遺族会の晴山宗規会長(78)=同市古川桜ノ目=ら県内の遺族会員6人。晴山さんは召集令状(赤紙)について「郵送ではなく、役場職員が直接届けに来て、受け取りを拒むことは許されなかった」と語り、市内から多くの人が出征し、叔父らが戦死したことを紹介した。
県立支援学校小牛田高等学園(菅原幸史校長)の生徒が手掛けた藍染め作品を並べた「コゴタブルー展」が、美里町近代文学館で開かれている。自然素材による深みのある作品群が、訪れた人たちを魅了している。22日まで。自己表現力を高める美術科授業の一環で、全校生徒63人が昨年4月に約800株の藍を校内の農園に植えた。同7月から9月まで4度にわたり葉を収穫し、水に漬け込むなどして染料を抽出。白い布を染料に浸し、美しい幾何学模様を表現した。展示会では、学年別にさまざまな手法で染め上げた作品約200点を紹介。布に載せた藍の葉をハンマーでたたいて染めた「たたき染め」や、棒に巻き付けて染めて雲のような模様を浮かび上がらせた「群雲絞り」が並ぶ。3年生が来月の卒業式向けに制作した卒業証書ホルダーもある。
大崎市の無形民俗文化財「金津流松山獅子躍」の稽古に励んでいる大崎市松山小(髙橋章友校長、児童数162人)で13日、その魅力と伝統を6年生が下級生に伝える引き継ぎ式が開かれた。6年生31人が務める最後の晴れ舞台に、下級生や保護者、学校統合に伴い春から一緒に学ぶ下伊場小4、5年生が熱い視線を送っていた。金津流獅子躍は、旧仙台藩領内に起源をもつ鹿踊(ししおどり)6種類の一つ。松山には江戸時代、地元の獅子躍組が金津流本流と言われる石関獅子躍組に伝授した記録があるが、明治時代に一度途絶えている。1993年に石関系統の金津流梁川獅子躍(岩手県奥州市)から伝授され復活し、94年に保存会を設立、現在まで継承。2023年3月22日、大崎市の無形民俗文化財に指定された。同校では総合的な学習の時間に、保存会(及川留太郎会長)から4年生は口唄歌、5年生は踊り、6年生は太鼓の指導を受けている。長いササラや獅子頭など重さ10㌔近い装束をまとい激しく舞う姿は、後輩たちの憧れの的となっている。
「NHKのど自慢大会」をまねた「THEのど自慢大会」が11日、大崎市古川穂波の大崎生涯学習センター・パレットおおさきで開かれた。県内外から集まった出場者たちは晴れ舞台で熱唱し、満員の聴衆とともに本物さながらの雰囲気を楽しんだ。