花鉢や野菜大好評

南郷高の生徒が育てた農産物販売会が8日、大崎市図書館で開かれた。心待ちにしていた市民で開始前から長蛇の列ができ、搬入されたシクラメンの花鉢、ダイコンやネギが飛ぶように売れ、生徒たちは忙しいながらも笑顔を絶やさず接客していた。同館が大崎地域の高校12校と締結している連携事業の一環。各校の図書委員が順番でお薦め本や学校の特色を紹介する展示コーナーがあり、今月は同校が担当。今シーズンは暑さの影響はあったものの、シクラメン130鉢をはじめダイコン、ネギも前回より品数を増やし、高品質のものを取りそろえたという。
触って遊べる作品展

古川幼稚園(大崎市古川中里、関純一園長)の「日々のあしあと展」が13日から、大崎市民ギャラリー・緒絶の館で開かれている。紙やプラスチック容器などが素材の触って遊べる作品展で、初日は同園の3~5歳児39人が会場を訪れ楽しんでいた。15日まで。遊具がある園をまるごと移設したような会場で子どもたちの創造性や探究心を多くの市民に見てもらおうと、20年以上続けている企画。ことしも4月から作品を制作してきた。年長児が作った迷路には冷蔵庫や自動販売機を置いた休憩所、疲れを癒やす温泉が作られ、ゴールした人だけが開けられる宝箱もある。年中児のコーナーでは、滑り台を利用したジェットコースターに順番待ちの列ができていた。年少児のファストフードショップは、細部までしっかり表現。絵画や藍染めも見応えがある。
古川東バイパス 12月21日 全線開通
東北地方整備局仙台河川国道事務所などは13日、大崎市の国道108号古川東バイパスが12月21日午後3時に全線開通すると発表した。中心市街地の混雑緩和と、それに伴う安全性向上、物流の効率化、救急搬送時間の短縮など、さまざまな整備効果を見込む。バイパスは古川鶴ケ埣を起点に、市街地を迂回し古川稲葉の国道4号に接続する5・1㌔区間で全線2車線。1990年度に事業着手し、2018年3月までに古川鶴ケ埣-古川宮内間の3・5㌔が完成、残る古川宮内-古川稲葉間1・6㌔の整備を進めていた。総事業費約340億円。また全線開通に先立つ10月31日、国道4号との接続部に当たる鴻巣交差点付近の市道大崎大通線が側道としてルート変更された。
78人が自慢ののど競う
五穀豊穣の守り神として信仰される箟岳山(涌谷町)を歌った民謡「秋の山唄」の継承を図る全国大会が9日、同町勤労福祉センターで開かれた。町主催、大崎タイムスなど後援。出場者たちが2部門で自慢ののどを競った。41回目のことしは、一般と寿年(75歳以上)の両部で実施し、前回の出場者が2人にとどまった少年少女の部は一般の部に統合した。東北を中心に関東や四国、九州から出場した78人が、「ハア」という歌い出しで歌声を響かせた。一般の部は、45人のうち10人が決戦会に進んだ。優勝したのは、第38回(2022年)少年少女の部で栄冠を勝ち取った佐藤美玖さん(15)=山形県寒河江市=。毎日3時間練習を重ねたといい、「優勝できてうれしい。歌唱にさらに磨きを掛けたい」と喜びを語った。
子どもの感性育てよう
美里町文化会館(早坂美名子館長)は、子どもの頃から生演奏に触れてもらおうと、町内の学校や幼稚園でミニ演奏会を開く取り組みを行っている。ことし5年目で、希望する施設は過去最多に上るなど〝音楽の輪〟が少しずつ広がっている。感性を育て演奏に対する興味を持ってもらうのを狙いに、2021年度に「音楽アウトリーチ事業」として始めた。県内の演奏者や団体が子どもたちの面前で演奏する。開催を希望する施設は徐々に増え、本年度は6施設の見込み。11日は、南郷小(鈴木資淳校長)で実施。仙台市を中心に活動する金管三重奏「ブラストリオ仙台」の3人が、ポップスや沖縄民謡、アニメソングメドレーを演奏。校歌の演奏では全校児童173人が斉唱し、会場は一体感に包まれた。
高校生が意見交換
大崎市内の高校生がまちづくりについて話し合う「高校生タウンミーティング×未来トーク」は9日、大崎市役所であり、約50人が学校、学年の枠組みを超えて意見交換した。生徒たちは「未来につなげたい大崎らしい豊かさ」をテーマに、市の若手職員らを交えて数人単位のグループで議論。「人の温かさと豊かな大自然」「学習しやすい環境」「おいしいご飯と温泉が自慢」など、それぞれの実体験に基づく市の魅力を挙げた上で「未来へつなぐ」方法と「自分ができること」を考えた。本年度開校した市立おおさき日本語学校を念頭に「国籍や性別、障害の有無を問わずみんな笑顔で暮らせるまちに」との声も。大人顔負けの発言の数々が職員らをうならせた。
「雨」の二面性を体験
国土交通省東北地方整備局主催の企画展「雨展」が13日から、加美町小野田図書館で開かれている。「あらぶる雨」「めぐみの雨」といった雨の二面性を体験型展示で楽しみながら学ぶことができる。16日まで。河川環境保全の大切さや雨の二面性を学習してもらうことを目的に、全国を巡回して開催。東北では7カ所で開かれ、同図書館が最後の会場。展示物は大学や気象キャスター、デザイナー、国交省職員らでつくる「水の巡回展ネットワーク」が制作。画面の前に立った人の動きに応じて光の雨が降ってくる映像や、タッチすると雨に関する音が流れてくるパネル、過去の豪雨災害の記録映像など9点が並ぶ。
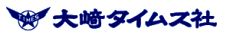
コメントをお書きください