抹茶味わいゆったりと

中秋の名月に思いをはせる月見茶会が9月28日、大崎市古川の祥雲閣で開かれた。参加者は数寄屋造りの本格茶室、龍華庵へ20人ほどずつ迎え入れられ、月夜とススキの模様で秋を表す和菓子と抹茶を味わい、室内のしつらえや茶器などの解説を聞きながら、ゆったり流れる時間を楽しんだ。大崎市祥雲閣茶道連盟が毎年開催している。足に不安がある人に配慮して椅子席も設けられ、市内外から約150人が訪れた。
髙橋さん 卒寿記念しコンサート

72歳でピアノを始めた大崎市古川若葉町、仙北製材所会長の橋義宣さん(90)が9月27日、同市古川のグランド平成でバースデー&チャリティーコンサートを開いた。会場には50人余りの聴衆が訪れ、橋さんの年齢を感じさせない演奏や歌声に声援を送っていた。橋さんがピアノを始めたのは、母親が入所していた施設を慰問し、利用者を元気づけたいという気持ちから。鍵盤を弾けず、譜面も読めない初心者だったが、熱心にレッスンに通い、3年後にはイベントで初演奏を披露した。この日のコンサートは9月4日に卒寿を迎えた記念として開いたもので、初回から数えて9回目。
大崎市 消防団の定員15%削減
大崎市は1日、市消防団定員をこれまでの2430人から15%削減し、2064人とした。担い手不足に伴う見直し。「実員数に変更なく、現状の地域防災力は維持される」(防災安全課)としている。市議会9月定例会に条例改正案を提出、原案可決された。市消防団は旧市町単位7支団編成。合併時(2006年)2519人だった団員数は少子高齢化、社会環境の変化などで減少傾向に歯止めがかからず本年度は1998人と、定員に対する充足率が81・8%まで落ち込んでいた。定員削減は実情を踏まえたもの。防災安全課によると、削減後も班編制やポンプ車運用に必要な実員数は満たしており、支団傘下の分団数も変わらない。
新米など15分で完売
美里町近代文学館で9月26日、図書館マルシェが開かれ、小牛田農林高の生徒が栽培した新米や西洋ナス「ロッサビアンコ」を販売した。市価より低く、高校生が熱心に育てたということもあって購入希望者が殺到し、15分で売り切れた。売り出したのは、農業技術科農業科学コース野菜専攻半の生徒たちが学習の一環で栽培したロッサビアンコと長ネギ、ササニシキ。3年生10人が、カウンターに商品とレシピ本を並べて販売に当たった。
大崎市 行財政改革推進へ
大崎市議会9月定例会は一般質問最終日の2日、5人が登壇し執行部をただした。予算編成で〝自治体の貯金〟に当たる財政調整基金の取り崩し依存が続く厳しい財政状況を指摘する質問に対し、執行部側は本年度から3カ年で取り組む「行財政運営の改革に向けた基本方針」を示した。議員は質問で、2015年度末に129億5000万円だった財政調整基金残高が本年度末21億2000万円まで落ち込む見通しを指摘。「残高減の原因検証が必要」とし「(行財政改革の)提案、実行計画を強いリーダーシップのもと断行すべき。市役所の決意を問う」と回答を求めた。
二次交通の充実を
官民一体で県内の観光振興を図る「みやぎ観光振興会議」の本年度最初の大崎圏域会議が9月30日、大崎市古川のグランド平成であった。来年1月に課税が始まる宿泊税を生かした観光振興策について委員16人と県側が意見交換。委員からは、運転士不足などに伴い確保が難しくなっている二次交通に関し、小型の乗り物などの導入に向けて支援を求める意見が相次いだ。
30回 節目の写真展
写真を楽しむ会「わいど」(小住正吾代表)の第30回写真展が、大崎市民ギャラリー・緒絶の館で開かれている。「わたしの出会い」をテーマにした作品など86点が展示されている。5日まで。同会は、地元の写真店に集まる仲間で設立。会の名称には、ワイドレンズのように視野を広げて楽しもうという思いが込められている。川田光子さんの「妖艶」は、暗い背景に真っ赤なツバメスイセンの花が浮かぶ一枚。「友人の庭で撮らせてもらった。とっておきの宝物」という。
オンラインで交流
大崎市と大阪府田尻町の田尻中が9月30日、オンラインで交流し、両校の生徒会が互いの学校を紹介したり、質問し合ったりして親睦を深めた。田尻中生徒同士の交流事業は大崎市になってから初めてで、約20年ぶりの再開となった。旧田尻町と大阪府田尻町は1991年、同じ自治体名が縁で友好都市提携を締結。東日本大震災時には大阪・田尻町から大崎市が消防車両、令和元年東日本台風時は段ボールベッドや消毒液などの支援を受けた。一方、台風21号(2018年)では大崎市が大阪・田尻町にブルーシート500枚を届けるなど、災害時に自治体間で連携してきた。児童生徒の交流は旧町時代、互いの町を訪問し、行ってきたが、近年はコロナ禍もあって関わりが薄くなっていた。昨年、自治体同士での交流を再開したことから、オンラインでの実施が実現した。
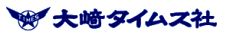
コメントをお書きください