大崎で一足早く出動式

県下一斉の「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」(21日~30日)に先立つ19日朝、大崎市と古川署、関係団体による合同出動式が市役所駐車場であり、約250人が〝安全安心なまち〟実現を誓った。出動式で、伊藤康志市長(=市交通安全推進協議会長)は「市民が悲惨な事故の当事者にならないよう、総ぐるみで一体的かつ強力な取り組みを展開していく」とあいさつ。式終了後、警察車両と交通安全指導車がパトロールへ出動。引き続き催された街頭キャンペーンでは「横断歩道は歩行者優先」「全席シートベルト着用」など標語入りサインボードやのぼり旗を全員で掲げ、通勤の車両や歩行者に注意喚起した。
心揺さぶる津軽三味線

プロの津軽三味線奏者によるコンサートが12日、涌谷町涌谷中で開かれた。全校生徒324人が巧みな生演奏を通して伝統和楽器の奏でる世界に触れた。音楽文化団体「民主音楽協会」(東京都)が、全国の小中学校と高校を会場に1973年に始めた。昨年末までに4700校、計140万人余りが参加したという。ことしから数年かけて東北地方1万人の参加を目指していて、この日が第1回となった。出演したのは、青森県鰺ヶ沢町出身の葛西頼之さん(37)、北海道帯広市出身の相澤裕斗さん(29)と千葉県出身のドラマー、大河内新太さん(43)。葛西さんは2015年に津軽三味線世界大会A級を3連覇したほか、海外公演は50カ国に上る。この日はドラムとの珍しい合奏のほか、自作の曲や津軽じょんから節、花笠音頭といった民謡、同校の校歌を演奏。演奏体験もあり、代表生徒3人が「さくらさくら」を弾いた。
65人が自慢ののど競う
「宮城菱取り唄全国大会」(大崎市鹿島台観光物産協会主催、大崎タイムスなど後援)が14日、大崎市鎌田記念ホールで開かれ、全国から集まった65人が自慢ののどを競った。その結果、一般の部は仙台市の会社員、鈴木怜菜さん(23)が優勝した。大会は、干拓前の品井沼(同市鹿島台)に自生していたヒシの実を漁師が取る際に歌っていた民謡「宮城菱取り唄」を歌い継ぐのを目的に始まった。31回目で、全国大会となってからは21回目。今回は少年少女の部(中学3年生以下)に5人、熟年の部(75歳以上)に25人、一般の部に35人が、遠くは愛知県から出場。このうち一般の部は、予選会を突破した15人が決勝大会に進出。歌詞2番までを2分15秒以内に歌い、「ハァここは渕花」の歌い出しで始まる歌を高らかに歌い上げた。
紙皿をタンバリンに
身近にある材料で楽器を手作りするワークショップが13日、大崎市民ギャラリー・緒絶の館で開かれた。参加した2歳児から小学生までの8人は紙皿を使ってタンバリンを作り、音を鳴らして楽しんでいた。15日まで開かれた同館の企画展「奏でる美術~音をみよう、形をきこう~」の関連イベント。市と宮城誠真短大が結んでいる包括連携協定に基づき、学生6人が子どもたちのサポートに加わった。タンバリンは、紙皿2枚を合わせた中にビーズや短く切ったストローを入れて閉じ、表面を鈴や毛糸、リボンで飾る。学生たちが授業で作ったものを改良した。子どもたちは紙皿に似顔絵や動物のイラストを描き、鈴やリボンの色にもこだわって製作。作業への集中力や手先の器用さで大人を驚かせると、完成品を振ったり、たたいたりして無邪気に喜びを表現していた。
小中学生が狂言発表
子ども狂言教室で練習を積んできた小中学生の発表会が7日、大崎市古川の祥雲閣で開かれた。緊張感と達成感が入り混じった表情で熱演する9人の子どもたちに、ここまでの努力を見守ってきた家族は温かな拍手を送っていた。本年度で11回目となる子ども狂言教室は、文化庁伝統文化親子教室事業の一環で、市内で活動する狂言教室基岩会が主催。7月に開講し、能楽師大蔵流狂言方、大藏彌太郎さんの指導を受け、これまで5回の練習を重ねてこの日の発表会を迎えた。上演したのは、48文字のいろは歌を学ばせようとする父親と息子の物語「以呂波」や「痿痢」など。中腰で膝を曲げる姿勢や正座は楽ではなく、言葉遣いや動物の鳴き声も現代と異なるが、子どもたちは練習の成果を発揮し、マイクを通さない生の声と体の動きで感情を表現。引き締まった表情で、600年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能を堂々と披露した。
新旧の遊びに夢中
美里町内の各種団体が一堂に会し、子どもたちにさまざまな遊びを体験してもらう「こどもふれあいまつり」が14日、町トレーニングセンターで開かれた。参加した児童らは輪投げやお手玉、ラダーゲッターなど新旧の遊びを通して地元の大人たちと交流した。幅広い年齢層の子どもたちが触れ合う場を設け、地域社会が一体になって育成を図るのが狙い。児童館や行政区長会、婦人会など15団体でつくる実行委員会が主催した。17回目の今回は折り紙や知恵の輪、竹とんぼ、琴演奏など約20種の遊びを用意。訪れた子どもたち約300人は各コーナーを回り、明確なルールの遊びに夢中になっていた。
心肺蘇生法など学ぶ
宮城労働基準協会古川支部は1、16の両日、普通救命講習会を大崎市古川の大崎建設産業会館で開き、計42人が応急手当てや救命処置について理解を深めた。救急医療などについて理解を深めてもらう「救急の日」(9月9日)に合わせて実施。16日は、同支部管内8社24人が参加した。参加者たちは、古川消防署救急係の職員2人の助言の下、人形を使って心肺蘇生法を体験。胸骨圧迫のこつや自動体外式除細動器(AED)の使用法、周りの人との連携の仕方などを学んだ。
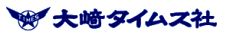
コメントをお書きください