建設の仕事に関心を

現場体験を通じ建設の仕事に関心を持ってもらおうという見学会が7月30日、大崎市古川字竹ノ内の県道改良工事現場で開かれた。子どもたちがミニショベルやドローンを操作体験し、建設業に対する興味を膨らませた。建設業のなり手不足が懸念される中、将来的な人材確保につなげようと、県と県建設業協会大崎支部が主催。都市計画道路稲葉小泉線の改良工事を県から受託している「丸か建設」(加美町)の協力で実現した。大崎地方を中心に親子連れ18組40人が、国道347号と同47号を結ぶ約1・6㌔区間を見学。工事の概要や進捗状況について県担当者の話を聞いた。子どもたちは重機や高所作業車に試乗したり、ドローン、ミニショベルを操作したりして機械や情報通信機器が現場で力を発揮し、重労働の軽減に役立っていることを学んだ。
夏休みの交通事故防げ

夏休みの児童を交通事故から守ろうと、古川署は7月29日、大崎市古川中央児童館で出前安全教室を開いた。児童館に通う小学生約100人が参加。交通課の署員が講師となり、自転車乗車時のヘルメット着用、車道飛び出しと交差点での事故を防ぐ「止まる(一時停止)」「見る(安全確認)」「待つ(安全確保)」の順守を呼び掛けた。また、夏祭りや花火大会など夜間の外出機会が増える時期をにらみ「車から見えやすいよう明るい服装を心掛けてほしい」とも。
心癒やす文化、芸術大切
日本文学研究者のロバート・キャンベルさんによる講演会が7月31日、大崎市鳴子公民館で開かれた。キャンベルさんは災害被災地や戦地を巡った経験を振り返り、人々の傷ついた心を癒やす文化や芸術の大切さについて語った。キャンベルさんが鳴子温泉地域に足しげく通うようになったのは、14年前の東日本大震災がきっかけ。沿岸部から二次避難してきた人たちに向け文学作品の読書会を行い、「心の復興」に尽力。その後も講演会やワークショップを何度も開き、地域との関係を深めている。コロナ禍後初の講演会となったこの日は、読書会を通じて被災者が明るさを取り戻していったことを紹介。能登半島地震の被災地で、芸術家たちが割れた九谷焼を使って新たな作品を生み出したことや、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナで、平和を願う日本の折り鶴文化を発見したエピソードなども披露した。
SDGs探究で大崎へ
「SDGs地域探究ツアーin東北」に参加した武蔵高等学校中学校(東京都練馬区)、桐朋学園(神奈川県鎌倉市)、栄光学園(同)の中高生14人が7月28日、大崎市を訪れた。一行は市地域交流センター・あすもで開かれた同世代交流に臨み、古川黎明高生が探究の授業で取り組んだ内容について意見交換した。同世代交流は、3校からの依頼でSDGsを学ぶツアーを企画したみやぎ大崎観光公社が、古川黎明高に打診して実現。まず市世界農業遺産未来戦略室の車田敦・副参事兼室長が講話。その後、グループワークを実施。古川黎明高3年の青木優奈さんと菅原未玖さんは、出荷規定外の「古川なす」を使ったパウンドケーキを開発し、フードロス削減と農家の増収を目指す取り組みを紹介。3校の生徒からは、ふるさと納税の返礼品も視野に入れた意欲作が高い評価を得た一方、「ナスの廃棄量がどれだけ減ったのか」「大量生産できるか」といった指摘もあった。
県内外の110チーム熱戦
大崎市古川の学童軟式野球チーム「大崎ジュニアドラゴン」主催の大会が7月27日、古川を中心にした市内20会場で開かれた。県内外から110チームが出場し、白熱した試合を繰り広げた。大崎ジュニアドランゴンは2011年に設立し、現在は小学1~6年22人が在籍。これまで数多くの全国大会で優勝や上位入賞を果たすなど実績を積み上げてきた。ことしも県スポーツ少年団軟式野球(ジャンボ大会)を制し、東北Ⅱブロック代表として軟式野球フェスに出場。同フェスで優勝し、全国大会進出を決めた。
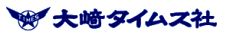
コメントをお書きください