格式高い築地塀発見

県多賀城跡調査研究所は3日、加美町鳥屋ケ崎宮前で発掘調査している「早風遺跡i地点」を報道関係者に公開した。同遺跡は平安・奈良時代の賀美郡の役所跡「東山官衙遺跡」(国指定文化財)の防御施設と考えられ、今回の調査で規模や構造が明らかになった。早風遺跡は、8世紀前半(約1300年前)に造られたと推定される東山官衙遺跡の北、東側に所在。東山官衙遺跡や、その周辺の「檀の越遺跡(街並み跡)」を囲む大規模な防御施設で、築地塀、土塁、堀で構成。蝦夷との緊張関係が高まったことから8世紀後半に造られたものとされる。発掘された築地塀は、土を少しずつ突き固めて積み上げる「版築」という工法で築かれた。東山官衙遺跡でも見つかっている格式の高い塀で、同遺跡で確認されたのは初めて。このほか、遺跡南側では土砂を採取するため地面に掘られた古代の土取り穴とみられる遺構、直径約60㌢の柱穴、溝も確認された。
七夕飾りで地域明るく

大崎市田尻の富岡自治振興会(菅原勝弥会長)は1日、手作りの七夕飾りを市田尻総合支所正面玄関に飾った。地域を明るくしようと毎年行っているもので、地元保育園児も訪れ、願い事を書いた短冊を笹竹に結んだ。新型コロナウイルスの感染が拡大していた2020年、早期収束の願いも込め、同会文化部が音頭を取って始めた取り組み。玉付きの吹き流しや折り紙のつるし飾りなどは全て会員の手作りで、毎年一部を作り直している。現在は田尻総合支所のほか、JR田尻駅と富岡生活改善センターにも飾り付けている。ことしは田尻総合支所に吹き流し9本、つるし飾りと人工の笹竹それぞれ1本を設置。田尻子育て総合支援施設「すまいる園」の5歳児35人が訪れて七夕飾りを見学し、「警察官になりたい」「原宿のお菓子を食べたい」などの願い事を書いた短冊を大人に渡し、笹竹に結んでもらった。
再エネを返礼品に
涌谷町は、4社と連携し、太陽光発電で得られた電力をふるさと納税の返礼品として提供する「再エネ×ふるさと納税」プロジェクトを始める。県内では初めて、全国的にも珍しい取り組みといい、古里に貢献しようという同町出身男性の思いから実現に至った。企画したのは同町出身で、仙台市で太陽光発電やオール電化を手掛ける企業の代表を務めた佐藤政彦さん(58) =同市=。関連企業に呼び掛け、太陽光発電システム販売施工「日本エコテック」(福島県)、電力小売「イーネットワークシステムズ」(東京都)と町を結びつけた。発電設備(発電量98・4㌔㍗)は、太陽光発電関連事業「ハンファジャパン」(東京都)が町に寄贈。太陽光発電システム用電力変換機器(パワーコンディショナー)は、電気機器メーカー「ダイヤゼブラ電機」(大阪市)が寄せる。エコテック社が今秋にかけ、同町太田の県道河南築館線沿いの町有地に発電設備を建設し、併せてふるさと納税の申し込み受け付けを始める。
高校野球宮城大会9日開幕
第107回全国高校野球選手権宮城大会(県高野連など主催)は9日、開幕する。甲子園出場を懸けた高校球児たちの熱い戦いが始まる。期間は14日間で決勝は28日、楽天モバイルパーク宮城(仙台市)で行われる予定。ことしは昨夏より4チーム少ない62校55チームが参加。県北部からは13校11チームが出場し、このうち2チームが4校による連合チーム。昨秋、連合初の県大会進出を決めた古川黎明と黒川、迫桜は今回、中新田を加えた4校連合で挑む。涌谷は南三陸、宮城水産、石巻北と連合を組む。県北部勢は、小牛田農林が9日の開幕試合で仙台東と対戦し、熱戦の火ぶたを切る。古川は10日、昨夏3回戦で顔を合わせた柴田と対決。勝ち進むと2回戦で仙台東-小牛田農林の勝者と当たる。
災害の避難所運営学ぶ
もしも自分の学校が避難所になったら-。避難所における高校生の役割を考える授業が6月30日、中新田高(早川健次校長)であった。3年生17人が避難所の種類や実情を学んだほか、段ボールベッドと簡易テントの組み立てを体験した。「命をつなぐ避難所運営」をテーマに、災害時に必要な力や備えを身に付ける同校独自科目「地域防災学」の一環。加美町危機対策課の職員2人が講師を務めた。職員は、「応急期(災害発生から3日間)」「復旧期(同1カ月程度)」「復興期(避難生活の長期化)」における避難所の役割、被災者が尊厳ある生活を営む人道支援活動の最低基準「スフィア基準」などを説明。また、能登半島地震の被災地で支援活動を行った職員が、当時の避難所の状況や東日本大震災との違いなどを語った。高校生が運営所でできることとしては、けが人や体調を崩した人の介助、救援物資の配給補助などを紹介。その上で「皆さんも被災者。まずは自分や家族を守ることを優先して」と訴えた。
絵手紙と切手展示
美里町駅東の沖田捷夫さん(80)が、自らしたためた絵手紙と集めた切手を町総合案内所(JR小牛田駅構内)に展示している。「80年生きてきた証しと、人生を支えてきた絵手紙を多くの人に見てほしい」と話す。沖田さんは62歳で退職後、町内の絵手紙サークルに入会。毎年200枚したためるのを目標に掲げ、職場の元同僚やサークル仲間へ送った。切手収集は小学校の頃に始め、一時中断したが、60歳まで続けた。展示会は、八十路の節目に合わせ自らの人生を振り返り、生きる糧にしようと企画。切手80点や絵手紙200点余りを掲げた。「人生花づくし」と題した絵手紙は「親の教えはきくのはな 人の悪口くちなしで 頭は垂れてふじのはな」などと含蓄に富んでいる。
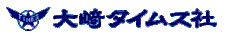
コメントをお書きください