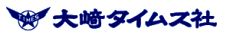政宗書状の臨書も

山形市の書家、佐藤綾夏さん(28)の書道展が、大崎市岩出山の「あ・ら・伊達な道の駅」スパイラルホールで開かれている。伊達政宗書状の臨書をはじめ、楷書や草書で書かれた作品が来場者の目を引いている。23日まで。小学2年生で書道を習い始めた佐藤さん。2023年、山形県白鷹町の特産品ベニバナのイメージキャラクター「紅花娘」になったことを機に、町へ恩返しをしたい、と本格的に書家としての活動を始めた。今回は半切、全紙、三尺六尺(縦約180㌢、横約90㌢)といった大きめの作品17点を展示。昨年11月の薬師まつり(栗原市築館)で、しづはた姫侍女役を務めた経験をもとに書いたものも並ぶ。表具は作品の雰囲気に合わせた色や模様を選び、着物を作る際の端材を使ったものもある。
形と組手で200人競う

第51回日本空手協会仙北地区空手道選手権大会(日本空手協会県本部仙北地区協議会主催、大崎タイムスなど後援)が3月23日、涌谷町B&G海洋センター体育館で開かれ、県北部の会員たちが上位大会進出を目指して稽古の成果を披露した。同会に登録している幼児から30歳代まで約200人が出場。競技は学年、男女別個人戦と団体戦の形と組手計49種目で、いずれもトーナメント戦。形の部では構えから踏み込み、中段突き、蹴りといった攻撃技と防御技の一連の動作を流れに沿って繰り出し、技の技術や力強さ、スピード、バランスなどを競った。
「鹿島台空襲」伝える
大崎市鹿島台の「鹿島台歴史研究会」は、第2次世界大戦末期に旧鹿島台村を襲った空襲についてまとめた冊子「鹿島台にも空襲がやってきた-1945年8月に米英軍機が東北を空襲」を刊行した。編集文責を担った鈴木光太郎さん(76)は「地方でも空襲の犠牲者がいた事実はほとんど語り継がれていない。戦後80年を機に事実を文字に残し、後世に伝えたい」と話す。同会の研究によると、終戦間際の45(昭和20)年8月9、10日、福島県沖の英空母から飛び立った艦載機4機が鹿島台村に襲来。蒸気機関車や鹿島台小校舎、民家に機銃掃射を浴びせ、自宅にいた30歳代と17歳の男性2人が亡くなった。県内では、仙台空襲(45年7月)が被害規模の大きさから広く語り継がれているが、鹿島台空襲については地元でも忘れ去られつつあるという。
稽古の成果発揮し熱戦
「第28回田尻少年剣道錬成大会」が3月30日、大崎市田尻総合体育館で開かれ、県内外から参集した少年少女剣士約500人が日頃の稽古の成果を披露した。小学生を対象にした同大会は、剣道に取り組む児童たちの親睦などを目的に、田尻剣友会と錬成舘が主催。試合は団体戦で、75チームが参加。5~6チームでリーグ戦を行い、各リーグ戦1位のチームが決勝トーナメントで優勝を争った。小学生剣士たちは、大きな掛け声を発しながら熱戦を展開。小学生として最後の試合となる6年生は、これまで磨いてきた腕前を発揮し、気迫のこもった攻防を繰り広げていた。
リメーク着物イケてる?
着物のリメークを楽しんでいる人たちによるファッションショーが3月29日、涌谷町涌谷公民館で開かれた。「みやぎ そよ風の会」の主催で、6年ぶり8回目の開催。素材の柄や色を生かした衣装を着こなしてのショーで過去最多の約400人の観衆を沸かせた。新たに設けたドレス部門を含む3部門に、町内外の幼児から99歳まで55人が出演。50年前の着物を再利用したドレスやワンピース、チャイナ服をまとい、ステージ左右に続いて客席中央のランウェイを優雅に歩いた。
加護坊桜まつり4日から
県内有数の桜の名所として知られる大崎市田尻の加護坊山で4日から、「第41回加護坊桜まつり」(同実行委主催)が開かれる。市田尻総合支所によると、満開は12~13日ごろを予想。昨年に続きライトアップが行われるほか、屋台も並び、花見シーズンを満喫できる。30日まで。「かんぼやま」の愛称で親しまれる加護坊山(標高224㍍)は、ドーム型の山頂が特徴。360度のパノラマが楽しめる山頂からは栗駒や船形、蔵王の山々や太平洋まで望むことができる。山頂へ続くなだらかな斜面にソメイヨシノやヤマザクラ、ベニザクラなど約2000本が植栽されている。文字通り「二千本桜」と称されており、この時期は薄ピンク色の花が山肌を埋め尽くす。
久しぶりのプレー満喫
大崎市田尻パークゴルフ協会は3月29日、地元の加護坊パークゴルフ(PG)場でオープニング大会を開いた。会員たちはことし最初の大会で腕を競い、男子は高橋貞二さん(百々・大沢・荒柳PG愛好会)、女子は浅間典子さん(北小塩PG愛好会)がそれぞれ優勝した。8回目となる大会には会員54人(男子39人、女子15人)が参加。「うぐいす」「うめ」両コースの36ホールでスコアを争った。4日前から続いていた暖かい天気から一転し、肌寒い一日となったが、参加者たちは元気いっぱい。寒さを吹き飛ばすような笑顔や笑い声を響かせ、久しぶりのプレーを楽しんでいた。
そり、寝袋など有料化
国立花山青少年自然の家は4月から、そりやテント、寝袋などの利用を有料にした。運営する独立行政法人国立青少年教育振興機構の経営が人件費や光熱水費、配送費などの高騰で急激に圧迫されているため。食事料金も小学生以上で値上げしたほか、日帰りで野外炊事や沢活動を行う客からも新たに料金を徴収し、運営費に充てる。