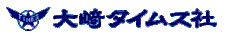藩政時代の大崎耕土描く

藩政時代開削の荒川堰用水路(色麻町、大衡村、大崎市)を描いた「荒川堰絵図」と絵図箱が、大崎市の指定文化財に加わった。市教育委員会は「仙台藩の新田開発の実態を示す資料。類例がなく大変貴重」として14、15日の2日間、市民ギャラリー緒絶の館(同市古川)で一般公開する。絵図は1858年制作。鳴瀬川右岸、現3市町にまたがる丘陵地を潤す総延長33㌔にも及ぶ長大な流路が幅50㌢、長さ18㍍の長巻物に。今もほぼ変わらない川筋をはじめ、計12カ所ある潜穴と隧道、田畑への配水口とため池、寺社を含む集落などが詳細に記され、市文化財保護委員の佐藤憲一さんは「藩が開削(1649年)から約200年経た荒川堰の現状把握と、度重なる飢饉を踏まえ用水路管理のため描かせたもの」と分析する。
冬空の下で熱かん

地場産缶詰をつまみに地酒を味わってもらう「冬空かんづめ居酒屋」が8日、美里町のJR小牛田駅東の駐車場跡地で開かれた。県内外から約400人が訪れ、寒空の下、熱かんで体を温め、一日限りの酒場の雰囲気を楽しんだ。「食によるまちづくり」をテーマに活動する町地域おこし協力隊の千代窪修一さん(40) や地酒屋「齋林本店」、水産加工製品製造販売「木の屋石巻水産」が初めて企画。会場には木の屋石巻水産の缶詰と町内の蔵元川敬商店の酒を並べた。訪れた人たちは、90㍉㍑入り酒器と初めの1杯、缶詰3種のセットを購入して居酒屋に参加。湯気が立つ1杯をぐいっと口に流し込んではカウンターで次の1杯を品定めするなど、飲み比べを楽しんだ。缶詰もクジラを中心にイワシやサバが並び、酒との相性を確かめる人たちの姿も見られた。
大崎市人口 前月比144人減少
大崎市は、今月1日現在の住民基本台帳人口を発表した。人口は12万2191人(男6万187人、女6万2004人)で前月比144人減少。世帯数も5万3120世帯で同24世帯減った。いずれも外国人(世帯)含む。このうち人口動態については、自然増減は出生47人(男24人、女23人)に対し死亡178人(男96人、女82人)で差し引き131人減。社会増減は転入203人に対し転出216人で13人減の転出超過となった。旧市町単位の地域別人口は、多い順に古川7万5502人(前月比34人減)、鹿島台1万714人(同20人減)、田尻9460人(同33人減)、岩出山9241人(同25人減)、三本木7252人(同9人減)、松山5226人(同9人減)、鳴子温泉4796人(同14人減)で、7地域全て前月より減少した。
親子ら陶芸に挑戦
里山を保全するため伐採した木や枝を釉薬として活用する陶芸作品作りが8日、加美町宮崎の旭地区地域づくりセンターで開かれ、親子らが思い思いの作品作りに取り組んだ。主催したのは、障害者就労支援などを行う同町の一般社団法人「もりの工房」。同法人は2020年に任意団体として設立し、昨年11月に法人化。里山保全活動で伐採した木などを活用した陶芸作品作りは初めてで、小児がん患者や知的障害児とその家族ら11人が参加。長年、陶芸に携わる仕事をしていた千葉ゆかさん(富谷市)の指導の下、植木鉢製作に挑戦した。親子らは手順やこつを聞きながら熱心に作業。手ろくろに粘土を乗せ、協力して形作っていった。