参道に咲いたハスの花

墓参りでにぎわうお盆の14日、大崎市古川沢田にある遍照院の参道に、薄い紙でハスの花をかたどったランタン100個が並べられた。日が落ちて辺りが暗くなるほどに美しさを増し、訪れた住民たちは一夜限りのライトアップを楽しんでいた。同寺院の護持会長、斎藤善清さん(75)が古川長岡地区公民館で開かれたランタン作り教室に参加し、美しさに魅了されたのがきっかけ。護持会の女性たちに協力を呼び掛け、同館職員2人も加わり、先月末から急いで100個を完成させた。この日は夕方から関係者が集まり、ランタンの色と設置する間隔のバランスを考えながら、参道の両脇に配置。前日のリハーサルを踏まえ、風に飛ばされないよう補強する工夫も施した。初の試みに、住民たちは「きれいだね」「お盆らしくてすてき」などと言いながら、スマートフォンで写真や動画を撮影していた。
よさこいや打ち上げ花火

栗原市内で高齢者や障害がある人たちが利用する施設を運営する豊明会(石橋侑子理事長)は11日、同市高清水の桂葉清水前農村公園で納涼夏祭りを開いた。施設利用者や家族、地区民が大勢集まり、よさこいや太鼓などの多彩なパフォーマンスや打ち上げ花火を楽しんだ。関連法人の弘慈会(小林恒三郎理事長)と共催して開催。同規模の催しはコロナ禍前以来で、準備する従業員たちも力が入っていた。元気いっぱいのよさこい演舞は県内外の3団体が共演し、地元でおなじみの劇団ともえ座は艶やかな舞を披露。築館薬師太鼓奉賛会の躍動感あふれる演奏に続いては、1050発の打ち上げ花火がスタート。漆黒の夜空に大輪の花が次々に咲くと、会場の空気は一気に熱を帯びた。
タマネギ生産拡大へ
加工業務用野菜の需要拡大を受け、県は水田を使った路地野菜の生産拡大を図っている。美里農業改良普及センター管内では来年、タマネギの生産面積が5年前の約3倍に急拡大する見込み。そこで同センターは5日、省力化の鍵を握る直播栽培についてのセミナーを美里町中埣コミュニティセンターで開き、農業者や農業関係団体計60人余りがポイントを学んだ。同センターによると、日本のタマネギ輸入量は年間約24万㌧で、生鮮野菜で最も多い。このうち9割を中国産が占めるが、近年は国産化ニーズが高まっている。単身世帯や共働き世帯の増加を受け、外食や中食が増えている点も需要を押し上げているという。同センター管内の作付面積は、2022年の4・1㌶からことしは8・7㌶へ急速に広がり、来年は12・1㌶が見込まれている。直播栽培は昨年産と本年産の約半分を占め、来年産は全体の3分の2に当たる7・9㌶に広がると予測されている。直播栽培は、移植栽培のような育苗と定植が不要で、播種機によっては畝立てと施肥を同時にでき、省力化につながる。一方で管内の気候条件などに最適な栽培技術が確立されておらず、導入品目としての経営判断が難しい点が課題という。
校章デザイン決まる
来年4月開校予定の加美町小野田小の校章デザインが、このほど決定した。小野田地区小学校統合準備委員会が審査を行い、東松島市の相澤航さんの作品が選ばれた。選出されたのは、小野田小の新たな出発を象徴し、調和と安定を意味する円形のデザイン。外側の円は「薬莱山と大地」「豊かな水源の鳴瀬川」「広く美しい空」「降り注ぐ満天の星空」「冬の雪」といった自然の恵みを表現。地域のシンボル薬莱山から昇る希望の光は、子どもたちが輝きながら成長していく姿を描いているという。小野田小は、東小野田小、西小野田小、鹿原小の3校を統合。校舎は東小野田小を使用する。
「初午まつり」の山車修繕
加美町はこのほど、伝統行事「火伏せの虎舞」で知られる初午まつりの山車3台の修繕費900万円を、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングで募る「山車復活プロジェクト」を開始した。第1弾として国内最大のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」で200万円を募る。花飾りなどで装飾された山車は、地元の小学生などが引いて中新田地区内を練り歩き会場を華やかに彩る、まつりに欠かせない存在の一つ。しかし、戦前から使い続けているものもあり、老朽化が進行。特に土台やかじ取りの部分がひび割れるなど劣化が激しく、このまま使い続けると山車自体が崩れてしまう危険性があるという。町はこれまで、会場などで改修費用の募金を行ったり、寄付を呼び掛けたりしてきたが、目標金額達成までには遠く及んでいない。そこで、650年以上続く伝統を次世代へ受け継ぐため、ガバメントクラウドファンディング活用に踏み切った。
戦争体験を次世代へ
「第26回ふるかわ平和のつどい」(ふるかわ平和のつどい主催)が15日、大崎市古川の吉野作造記念館で開かれた。約40人の参加者は正午に戦没者へ黙とうをささげた後、平和作文コンクール受賞者の朗読や、地元出身のオペラ歌手・喜久間あやさんの歌に耳を傾けた。主催者の佐藤昭一代表世話人は国内外の情勢に触れ、「平和は誰かに任せたりせず、戦争体験世代から託されたバトンを受け止め、粘り強く語り継ぐ努力を続けなければならない」とあいさつ。
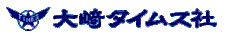
コメントをお書きください