こけしの絵付けに挑戦

大崎市鳴子小中の5、6年生41人が8日、同校で鳴子こけしの絵付けを体験した。地域の伝統工芸に触れてもらう取り組みで、児童たちはこけし工人から指導を受けながら、真剣なまなざしで木地に顔や模様を描いていた。こけしの絵付け体験は市鳴子総合支所地域振興課が企画し、学校統合前から毎年実施。この日はこけし工人の大沼秀顯さんと柿澤是伸さん、市地域おこし協力隊員でこけし工人見習いの渡辺あかねさんが講師を務めた。子どもたちは黒、赤、緑の塗料を筆に取り、教えられた順番で高さ約20㌢のこけしに眉毛や目、鼻、髪などを描いた。胴体は伝統的な菊の花模様を描く児童がいる一方、ひらめきに任せて自由に筆を走らせる児童もいた。
親睦重視の運動会

大崎市古川の高倉地区民運動会(高倉地区振興協議会主催)が6日、旧高倉小体育館で開かれた。住民同士の親睦を重視し、10行政区を4チームに分ける新たな編成で、未就学児からシルバー世代まで200人余りが競技を楽しんだ。これまでの行政区単位で順位を競うことを改め、2~3行政区でチーム編成し、親睦を深める場に刷新。実行委員は30、40代の若手が多く、競技は全ての世代が参加できるよう工夫した。人数制限のない借り物競走は年齢別の6区分あり、未就学児は保護者が抱いて走っても良いルール。大玉送りでは世代や身長が異なる住民同士が声を掛け合い、チームワークでボールをつないだ。
市民の〝生の声〟傾聴
大崎市議会の「議会報告・意見交換会」が7日始まり、議員と一般市民が活発に意見を交わしている。誰でも参加自由。14日以降は市内7カ所で行う。初日は市図書館(同市古川)であり、議会運営委員会と各常任委員会の議員合わせて8人が出席。議会の主な取り組みを報告後、「子育て環境」「公共交通利用(大崎市をもっと暮らしやすくするために)」の2テーマで意見や提言を受け付けた。市民側からは「子ども会」が相次ぎ消滅している問題への危機感や、住民バスの利便性向上、市内数カ所での運行にとどまる予約型乗り合いタクシー(デマンドタクシー)を拡張すべきとの声が上がった。「子ども会も(市教育委員会が地域移行を進める)学校部活動と同じく地域の団体・組織を受け皿にしてはどうか」との指摘も。
横断歩道も気を付けて
涌谷町の園児を対象にした「こじかクラブ交通教室」が6月中旬から計7日間にわたり、涌谷自動車学校で開かれ、横断歩道の正しい渡り方やシートベルトの大切さを学んだ。4日は涌谷南幼稚園の全園児12人が参加。自動車学校職員が教習車と子どもの人形を使い、道路への飛び出しの危険性や正しいシートベルト・チャイルドシートの着用の仕方を実演した。
健康ゲーム指導士養成
eスポーツ(健康ゲーム)を使い元気と長寿を支援する健康ゲーム指導士の養成講座がこのほど、栗原市高清水の特別養護老人ホーム桂葉で開かれた。施設を運営する豊明会と、関連法人の弘慈会の職員約20人が受講。実技を中心に、機材の操作や盛り上げ方も学んだ。健康ゲーム指導士は、日本アクティビティ協会(横浜市)の認定資格。施設同士または在宅と施設でのオンラインゲームが可能で、コロナ禍に広がった。指導士は全国に約5000人おり、対面での講座は県内でほとんど開催例がない。講座では、ゲームセンターや家庭用ゲーム機でおなじみの「太鼓の達人」を使用。ゲームと縁が薄い高齢者も太鼓をたたく動きには親しみがあり、挑戦しやすいことから取り入れた。受講者は、プレーヤー、説明する職員、観客の役を交替で体験。リズムに合わせて手をたたく動きを観客に促すと、全員参加型の雰囲気がぐっと盛り上がった。
水辺空間の活用PR
水辺環境の活用をPRする社会実験イベント「水辺で乾杯2025」が7日、全国で行われた。大崎市鳴子温泉の鳴子ダムでもダム管理所職員や市職員らがダム天端で乾杯し、大崎地方の治水、かんがい用水確保を担う鳴子ダムをアピールした。水辺で乾杯は、「川の日」(7月7日)にちなんだ官民協働プロジェクト「ミズベリング」の一環で、2015年から続くイベント。水辺の新たな活用法を創造する機運を醸成しようと国土交通省が推進しており、昨年は全国264カ所で約2万人が乾杯した。鳴子温泉地域は昨年から参加しており、ことしはダム管理所の小嶋光博所長と職員、市鳴子総合支所の今野冨美支所長ら市職員とその家族ら計17人が参集。全員が青色のシャツやタオルなどを身に着けて午後7時7分、飲料と横断幕を掲げて乾杯し、その様子をドローンで撮影した。
日本語学校に理解
大崎市古川第三小(児童数726人)で7日、市立おおさき日本語学校を学ぶ総合学習が開かれた。4年生142人が日本語学校の校長から話を聞き、学校の特徴や役割、国際交流について理解を深めた。同校から徒歩約10分の距離に日本語学校の学生寮があることから、国際交流のきっかけづくりにと企画。講師を務めた日本語学校の鈴木俊光校長は、学校行事は小学校とほぼ変わらないことや、学生はそれぞれ日本とは異なる文化や宗教を持つこと、日本での就職や進学など大きな目標を持って入学したことなどを紹介した。児童たちは興味深そうに話を聞き、地図帳で学生の出身国であるベトナム、インドネシア、台湾を探したり、昼休みが60分もある時間割を見てうらやましそうに声を上げたりした。質疑応答では「(学生たちは)なぜ大崎市の日本語学校を選んだのか」「どうして小学校の校舎を使ったのか」など、次々と質問を投げ掛けていた。
64事業所で職場体験
職業観や仕事への理解を深めようと、大崎市古川中の2年生194人が3日から2日間、市内計64事業所で職場体験を繰り広げた。古川署には「将来は刑事に」「白バイ隊員が憧れ」などと意欲満々の5人が訪問。制服試着やパトカー試乗をはじめ、実際の鑑識活動と同じくアルミニウム粉末を使った指紋採取も体験するなど、地域の「安全安心」を守るさまざまな警察業務に次々と挑んでいった。4日午後は道の駅おおさき(同市古川)で交通安全街頭キャンペーンに一役。大雨が降るあいにくの空模様だったものの、「安全運転お願いします」「気を付けて」と生徒たちが張り上げる声は雨音にも負けないほど。用意した啓発グッズはまたたく間に〝完売〟した。
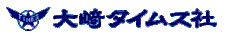
コメントをお書きください